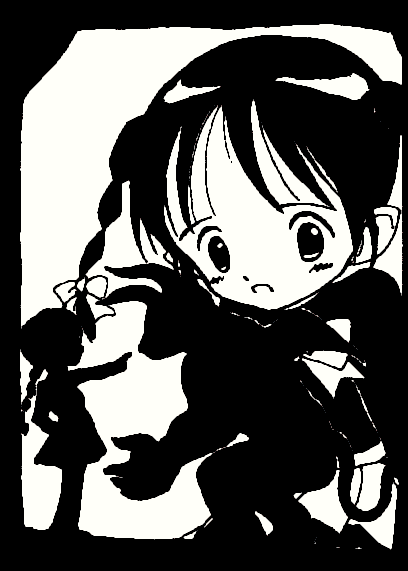
This short storys
based upon " Ressya monogatari "
created and illustrations by Mr. K.Murayama
One Drop Theater
それは時が朝から昼へと移ろうとしていた頃だった。
ガタン・・・ゴトン・・・ガタン・・・ゴトン・・・
いつものように規則正しい旋律を響かせながら列車が走っていた頃だった。
かたかたかたかた・・・
その中でいつものように規則正しい・・・
か・・・かた・・・かたん・・・かた・・・かたかた・・・かたかたか・・・ん・・・
とは少し言い難いワードプロセッサーの響きを一人の少女が奏でていた頃だった。
「ねー、おねーちゃーん。お話ー!お話ちょーだい!」
「へっ!?」
いきなりだった。
その声に思わず少女の手が止まった。
その途端ワードプロセッサーのディスプレイに紡がれつつあった物語も止まった。
「えっ・・・な、なに?」
そして少女は反射的に顔を上げると、その声の方へと視線を向けた。
「えへへー、こんにちはー!」
それは屈託のない笑顔だった。
席に着いたまま向けた少女の目線と同じ高さにあった笑顔だった。
「こ、こんにちは。」
少女はややうわずった声を上げながらその笑顔に挨拶をした。
それは小さな子供だった。
赤茶けた髪と大きな鳶色の目をした5〜6歳ぐらいの小さな女の子だった。
「ねーねー、おねーちゃん、おねーちゃんってお話作ってる人でしょー?」
「え、ええ・・・そうよ。」
「やったー!、じゃ、これあげるから私にもお話ちょーだい。」
やはりいきなりだった。
かつては自分もこんな頃があったのかも・・・という感慨に少女が耽る間も与えない程の
好奇心を全面に押し出したその声と共に小さな手が少女の前に差し出された。
「えっ?これ・・・」
そこには一粒の飴玉が乗っていた。
その小さな手に相応しい、薄紅色の袋に包まれた小さな飴玉だった。
そして少女の目には自分が断ることなど欠片も考えていない無邪気な笑顔が写っていた。
「ええっと・・・そうねえ・・・」
勿論・・・それは正解だった。
「それじゃあ・・・ちょっとそこで待っててね。」
そういうと少女は少しすました表情を作りながら再びその指を動かし出した。
・・・勿論、紡ぎかけの<物語>を保存することを忘れずに。
かたかたかたかたかたかた・・・
その間・・・ほんの数分ほど・・・
「・・・じゃ、はいこれ。」
やがて少女はその声とともに紡いだばかりの一枚の紙片をその子に渡した。
「わーい、おねーちゃんありがとー!」
その声と共に持たされた紙片をひらひらとさせ、別の車両へ走り出した姿を見送りながら、
少女は先程受け取った報酬を改めて口に入れ、再び紡ぎかけの物語へと戻っていった。
かたかたかたかたかた・・・
その甘さが心地よく広がって行くのを何処か楽しげに感じながら・・・
そして・・・それから大体一週間が過ぎた頃・・・
TON!
邪悪に顔を歪ませた巨体の悪魔が動き出す。
「わはははは。その姫君を儂に寄こせ。されば汝の望みを叶えよう。」
TATATATATAN!
KAKAKAKAKAN!
「黙れこの悪魔め。我の聖なる剣に叶うと思うてか。」
正義の騎士が勇気と剣を奮いながら立ち向かう。
・・・はぁぁぁ・・・
KOKOKOKON!
POPOPOPON!
「悪魔よ下がりなさい。その身が今生で潰えるのを望まぬのなら。」
騎士の背に守られた姫君が毅然とした態度で悪魔にそう告げる。
・・・ひゃぁぁぁぁ・・・
TONTANKON!
KANKANTON!
「この・・・この身の程知らずの愚か者共が!今よりその身で恐怖を知れ!」
悪魔が巨体を揺らしながら二人に迫る!
・・・ふぇぇぇぇ・・・
PONTONTANKAN!
TONPONKANTAN!
「悪魔よ。永劫の闇と共に滅びよおおお!」
騎士も負けじと歩を向ける!
・・・へぇぇぇぇぇ・・・
PONKONTONPONKANTON!
KANTONKONPONTANKAN!
・・・小刻みに音が響き続けていた。
その世界を形作る、かりそめの命の根幹たる音だった。
その鞄の端をあらゆる歩調を用いて叩き続ける二人分の指が生んだ音だった。
それは小さな世界だった。
平たい鞄の上に繰り広げられた紙の世界だった。
ほんの少し前、二人分の手によりあっという間に生み出された世界だった。
・・・ほぇぇぇぇ・・・
その世界を目の当たりにした少女は文字どおり固唾を呑んで見守るだけだった。
無理もない。
それは前に少女が目にした、紙を即興で切って物を形作る「紙切り芸人」よりも上手で。
それは前に少女が楽しんだ、自由自在に人形を操れる「人形使い」よりも上手で。
それは前に少女が耳にした、鉱石ラジオで語りを生業とする「声師」よりも上手で。
それは小さな舞台。
先程少女の目の前で切ったばかりの紙で鞄の上に設えられた小さな劇場。
それからその舞台に相応しい大きさの、同じく紙を切ることで作られた幾つもの人形達。
しかし、それは同時にあの驚異的な指の織りなす微妙な振動が生み出す目の錯覚、そして
同時に発せられる何種類もの声色をもってその舞台の中で演技を行う役者達。
そう、それはあの・・・
何でもその昔、政情不安な王国で長期の地下暮らしを余儀なくされた王族達が連れてきた
芸人がその狭さをカヴァーするために生み出したのとか、旅行好きの王族がやはり連れて
きた芸人が馬車のような狭い場所でも行えることが出来るようにと考え出されたのが起源
だとか色々諸説はあるが、いずれにせよ由緒は正しく、そしてその芸そのものの性格から
それこそ上流階級や、最低でも一部の大金持ちしか実演を見ることが出来無いと言われ、
一般庶民には作り話とさえ言われている・・・
通称「紙切れ劇団("Paper troupe")」と呼ばれる、正しく”芸”術集団だったからである。
目の当たりにした少女が、感嘆が沸き続けるのを止められなかったのも無理はない・・・
やがて・・・
「さてお客様。舞台は佳境に入らんとしておりますが、劇団員のお色直しにしばしの時を
頂戴したく、これにて第一部を幕とさせていただきまする。」
ご丁寧にも舞台の裾から出てきた老紳士の紙人形がそう告げ終わると共に、少女の前から
穏やかそうな声が聞こえてきた。
「・・・さてお嬢さん、如何でしたかな?」
「・・・は、はいっ!」
その紳士の声とともに少女の視界にそれはやっと認識された。
組立式の台に乗った何処にでもあるありふれた平たい革製の鞄。
その上に並べられた大小さまざまの紙切れ。
そして、少女に向かって穏やかな表情を向ける三十代半ばの上品そうな男女の姿・・・
少女はここが長い旅路を走り続ける列車の中で、外では星々と共に大きく丸い月が辺りを
照らしている時間で、そして今、自分がこの公演の唯1人の観客だったことを思い出した。
「初めて見ましたけど・・・すごくすごく・・・すごかったです!」
「ははは、ありがとう。お嬢さんに気に入っていただけて嬉しいよ。」
そう言うとその紳士は上品そうな嫌みの全くない笑みを少女に向けた。
「お話に無理は無いかしら?貴女のイメージどおりになっているかちょっと気になるの。」
紳士の隣に座っていた婦人が何処か不安げにそう言った。
「い、いえ、そ、そんなことは・・・」
「いただいたお話じゃ少し短すぎたもので色々付け加えちゃったけど・・・ごめんなさい。
気になるところがあったら幾らでも直すから遠慮無く言ってね。」
「わ、私の話なんか・・・」
その態度に少女は恐縮するばかりだった。
それは今日・・・この時から半日ほど前からそうだった。
いつものように物語を綴っていた少女の元にこの二人が訪れ、自分達が飴玉と引き替えに
物語を渡したあの女の子の両親であることを告げると共に、その物語をとても気に入った
娘に懇願され、芸人である自分達がちょっとした劇にしてみたので是非見に来て欲しいと
告げられここに来てからそうだった。
しかしその当の本人と言えば・・・
「やれやれ・・・どうしてもやってくれって頼んだ本人がこれだからな。」
少女がそう苦笑する紳士と一緒に後ろ側の席に目をやったとき、一枚の紙片を握りしめた
まま、小さな寝息を響かせているあの女の子の姿が写った。
「はは、私もまだまだ修行が足りないということかな?」
「そうよあなた。覚えてるでしょ?・・・この子ったらお嬢さんにお話を頂いたその日は
寝かしつけるのが大変なくらい面白がっていたんですよ。」
「おいおい、今回のこの話の演出は君の担当だよ。」
「あら、そうでしたっけ?・・・でも芸人としてのしつけは貴男の担当ですよ。」
「うーん、それを言われると辛いな・・・」
困った口調ながら笑顔のままそういうとその紳士はその寝息にそっと近づくと優しく抱き
かかえ、元いた場所まで再び運んできた。
「う・・・うん・・・あ・・・お父さん・・・おはよう・・・」
「おはよう・・・はは、今日みたいに寝付きが良いと私達も楽なんだけどね。」
「ほらほら何時までも寝てないで・・・ほらお姉さんも待ってるわよ。」
「えっ?・・・あ、お姉ちゃん・・・あー!お姉ちゃんだー!おはようお姉ちゃん!」
「お、おはよう。」
先程までの穏やかなやりとりに加え、まるで人形のように安らかな寝顔を見せていたのと
対照的なその元気な返事に少女は別の意味で驚かされた。
「えへへー、お父さんとお母さんすごかったでしょー!」
「う、うん。」
「それじゃ今度は私の番だからもっとすごいから楽しみにしててねー」
「えっ?」
そういうとその子は紳士の手から廊下に降りると自分の鞄から一枚の紙切れを取り出し、
やがて両親が先程少女に見せたのと同様に何かの形に切り出した。
二人とは比べ物にならないほどぎこちない手つきながら・・・一生懸命に・・・
「・・・実は次の公演を娘のデビューにしようと思ってね。」
「へえ、そうなんですか。」
「まあ、まだまだとても人にお見せするレベルじゃないと思うんだけど、客観的に見ても
スジは悪くないみたいだし、駅に到着するまでには何とかなると思ってるわ。」
「そうなんですか。きっと大丈夫だと思いますよ。」
「ありがとう・・・ところで一つ許して欲しいことがあるんだが・・・」
「・・・はい?」
どことなく詫びるような表情を作った二人の意図が解らないまま少女はそう言葉を発した。
「娘のデビュー作には本人が一番気に入っている話と思ったんだが・・・ちょっと適当な
役が無くてねえ。第二幕は私達の完全なオリジナルになってしまったんだよ。」
「えっ?・・・」
「ごめんなさい。原案者としてあなたの名前をきちんとお客さんに告げると言うことで許
して貰えるかしら?」
「えっ・・・あの・・・」
少女は再び思い出した。
これが上流階級や一部の金持ちの前でしか行われないお芝居だということを。
そして想像した。
その場所に自分の名前が・・・
・・・
・・・
・・・!
・・・!!!・・・!!!!!
「ええええええええええええええええっ!!!」
驚くばかりの声だった。
無理もない。
既にお芝居ということで加えられた脚色、そしてその見事としか言えない演出によって、
これが自作を元にしているとは信じられない程になっているのを目にしたばかりなのだ。
その上、この作品は元々たった飴玉一粒分の・・・
そうでなくても自分の作品に対する少女の評価は・・・
幾らお世辞だと思っていても・・・
勿論少女は慌てて撤回するように二人に申し入れた。しかし・・・
「じゅんびできたよー!」
「はは、じゃまずはゆっくり見てから決めて貰おうかな。」
「そうそう。まずはゆっくり楽しんでからね。」
その小さな声と二人の声に押し切られたかのように取りあえず再び観客となることとし、
そして不安と幾ばくかの期待の中・・・未知の第二幕は始りを告げた。
一触即発悪魔と騎士。
巨体を揺らして恐怖をばらまくにっくき悪魔。
銀の剣を振りかざし、勇気を奮いし正義の騎士。
さてその結末は・・・
PONTONTANTAN!
先程と同様に見事としか言えない手練が少女の目の前で繰り広げられていった。
・・・
しかし、先程とは違って幾分目の慣れた少女には先程の驚きは感じなかった。
鞄は鞄、紙は紙・・・そうでないと思わなければそうとしか見えなくなっていた。
<慣れ>というのはこういうことかと少女は幾ばくかの残念さを感じていた。
・・・だが、それはほんの錯覚にしか過ぎなかった。
「はいカット!・・・だめだめだめだめじゃないそんなんじゃ!」
紙の舞台の裾からその小さな女の子が出てきた時、少女の顔は先程以上の驚きに彩られた。
「!!!・・・ええっ!?」
生きていた。
まさしく生きていた。
紙の人形の筈なのに、それは正に生きているとしか思えない動きで登場したからだ。
「演技も今一つだし、何より台詞が棒読み・・・私のシナリオを駄作にしたいの?」
「す、すみません。で、でもこれでも僕、一生懸命やってるんですよ。」
大上段に構えていた筈の悪魔がその女の子に頭を垂れた。
その情けない仕草・・・それは先程とは比べ物にならないほどの自然なものだった。
「お、俺の何処が悪いんですか?悪いとこあったら何でも直しますから許して下さい。」
「悪いとこって・・・それは良いところのある人に言うことよ。」
誇り高い正義の騎士が鳴きそうな声で少女に語りかける。
その焦った様子や困惑する表情までが当たり前のように感じられた。
・・・こ、これ・・・
その様子に少女は言葉を失った。
さっきのは言うならば声色と指の動きで見せる人形劇・・・
しかし今、目の前にある光景はそんな言葉すらとっくに越えていた。
何種類もの声はもはやそれだけでそれぞれの人格を表すが如き真実味を感じさせ、そして
もはや少女の耳では感知できなくなった程の細かな指の動きは、紙切れに命を与えている
魔法のリズム・・・いや命の脈動そのものだった。
少女はやっと気付いた。
これが劇団を舞台にした芝居で、先程のが<下手な芝居>をやっていたことに。
その上、或る意味それ以上に少女を舞台に釘付けにしたもの・・・
それはその言葉に右往左往し、緊張の余りどんどん劇を滅茶苦茶にして行く<劇団員>を
前に、何とかしようと舞台狭しと動きまくる女の子・・・真の<主役>の姿。
そう、それは・・・
その姿といい声といい、少女を含めて誰がどう観ても間違いようのない・・・
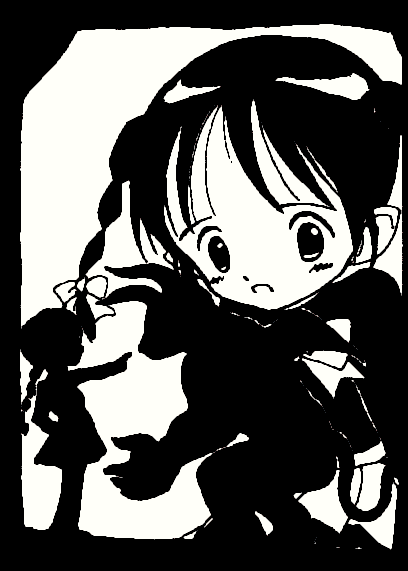
小さな・・・<自分>・・・
列車は夜を走っていた。
満月の下を規則正しい輪音を響かせながら走っていた。
そしてその客車の一室の、色々思うこともあった少女が取りあえず行っていたのは・・・
「う、ぷぷ・・・くく・・・あ、あははははははははは!」
その<喜劇>に対する最大の評価の<笑い声>を響かせ続けるということだった・・・
END
この作品はK.Murayamaさんの著作「列車物語」を元に私が創作した作品です。
なお、この作品を掲載することを快く承諾していただきましたこと、そしてお忙しい中、
この作品に対しても挿絵を描いて頂いたご本人に対し、この場を借りてお礼申し上げます。
K.Murayamaさん、ありがとうございました!